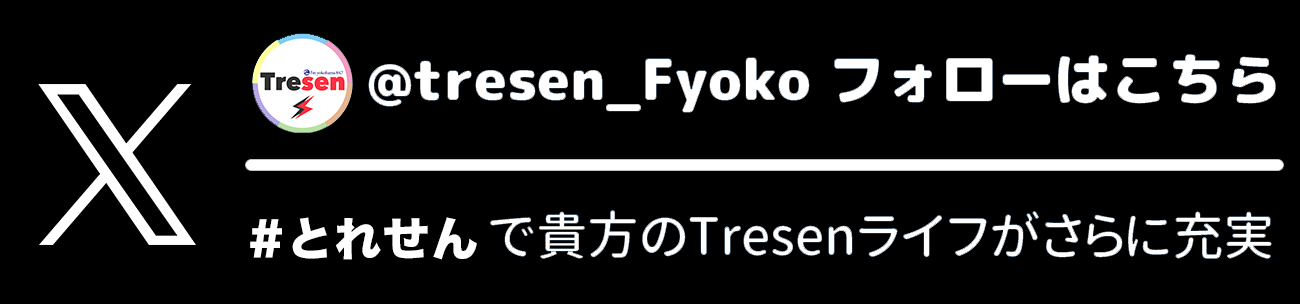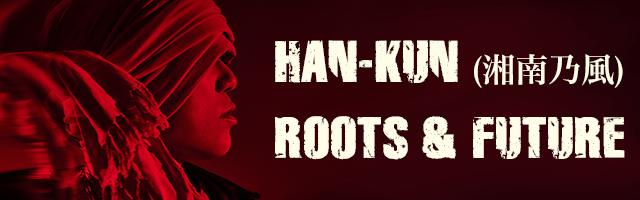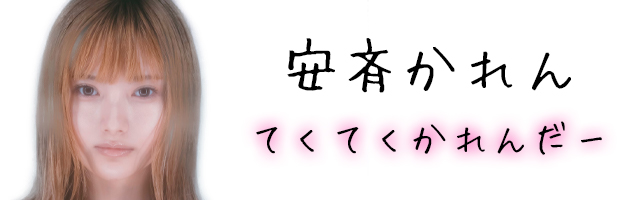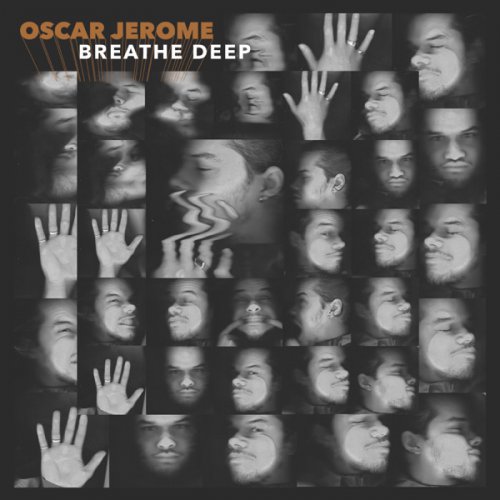人気者は誰だ!?
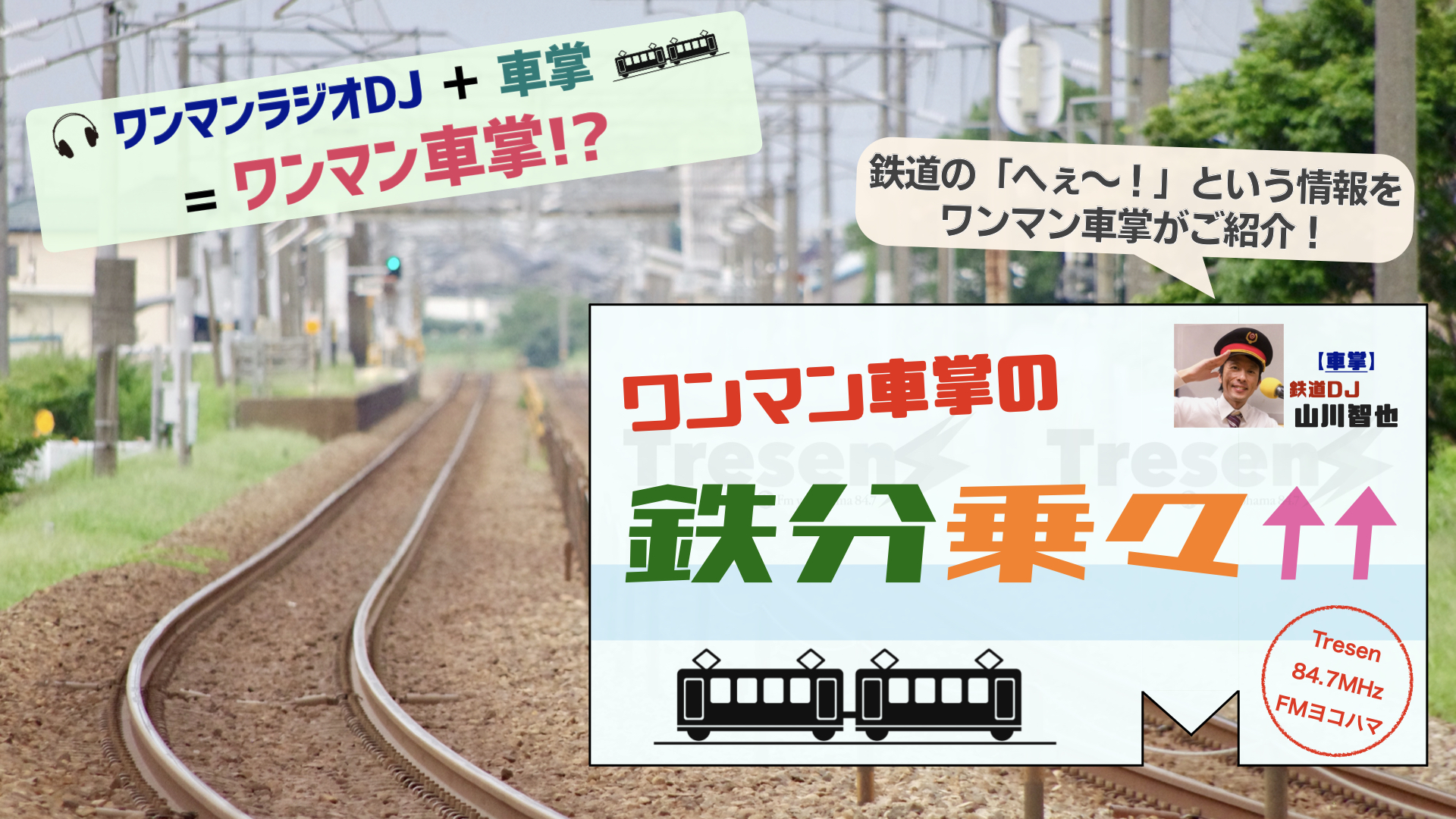
鉄道開業の地・横浜から、
今日も鉄分が上がっちゃう話をお届けします!
ワンマン車掌の鉄分乗々↑↑
今日は・・
「人気者は誰だ!?」
です。
先月末、国土交通省が昨年度の都市鉄道の混雑率調査結果を公表しました。
この調査では、まず、各路線の最も混雑する区間を設定します。そして、その区間が最も混雑する1時間に用意している輸送力に対し、実際にどのくらいのお客さんを輸送しているかの割合を算出しています。
今回発表された結果によると、1位は東京都の荒川区や足立区などを走る「日暮里・舎人ライナー」で、赤土小学校〜西日暮里間が7:30〜8:30で177%の混雑率となりました。
この日暮里・舎人ライナーは、日暮里から見沼代親水公園までを結ぶ路線で、2008年に開業した比較的新しい路線です。もともとは、交通手段がバスしかない鉄道空白地帯だったエリアをカバーしており、開業後、沿線は急速に発展していきました。
一方で、この路線は、ゆりかもめやシーザイドラインのような新交通システムのため、車両は小さく、増結も難しいなどの理由から、近年は連続で混雑率1位を記録しています。
また、関東エリアだと、この他、JRの中央線快速や埼京線、東京メトロ日比谷線などが160%超えを記録しているほか、東海道線や京浜東北線、総武線快速や南武線など多くの路線で150%台を記録しています。

東京以外の都市は、ほとんどの路線で100%〜140%程度に収まっているので、やはり東京の鉄道の混雑率は高い事がわかりますが、10〜20年前は混雑率上位の路線は180%超えは当たり前で、路線によっては200%を超える路線もあり、これでも近年はかなり数字的に改善しています。
混雑率改善の理由としては、大きく分けると鉄道会社側によるものと、利用者側によるものに分かれ、鉄道会社側の理由としては、信号システム改良などによる列車本数増加や、車両の長編成化によるものなどが挙げられます。また、東京メトロ副都心線やJRの上野東京ラインのように、新しい路線や直通サービスが誕生したことで、並行する路線の混雑が改善したケースなどもあります。

一方、利用者側の理由としては、「朝活」などのブームで最混雑時間帯を避けた分散利用者が増えたほか、コロナ禍を経験して働き方に変化が起きている点などが挙げられます。
ただ、この数字はあくまで最混雑時間帯1時間の平均値なため、全ての列車がこのパーセンテージというわけではなく、もちろん、このパーセンテージよりも混んでいる列車もあれば、空いている列車もあります。
また、同じ列車でも、進行方向前寄りの車両は混んでいるけど、後ろ寄りの車両は多少余裕があるなど、各路線にはその路線特有の「混雑のムラ」が存在します。
例えば、県内を走る東海道線は最大で15両編成の列車がやってきますが、4号車と5号車がグリーン車なので、その前後の3号車と6号車は、グリーン車を避けたお客さんが集中して特に混雑しやすい傾向があります。

また、ターミナル駅など利用者が多い駅の階段や改札に近い位置の車両も混雑しやすく、これらを避けるだけでも、混雑のストレスは大きく変わる可能性があります。
利用者が多いという事は、それだけ人気とも言えますが、出来るなら、座れなかったとしても快適に過ごせるくらいの混雑であってほしいですよね。皆さんも、乗車時によく周りを見渡してみると、「実は、混んでいるのは自分が乗っている車両だけ」という事もあるかもしれません。少し、意識してみてくださいね!
今日もご乗車ありがとうございました!
この回の模様は、8月19日(火)の29時まで
radikoの↓タイムフリー↓で聴けます!
コーナーは18:00ジャストから始まってます!
来週もお楽しみに!
ひとつ前の記事
「Take a picture♪」 #安斉かれん #てくかれ(安斉かれん てくてくかれんだー)ひとつ新しい記事
8月20日(水) ゲスト:スピラ・スピカ(本日のTresen)